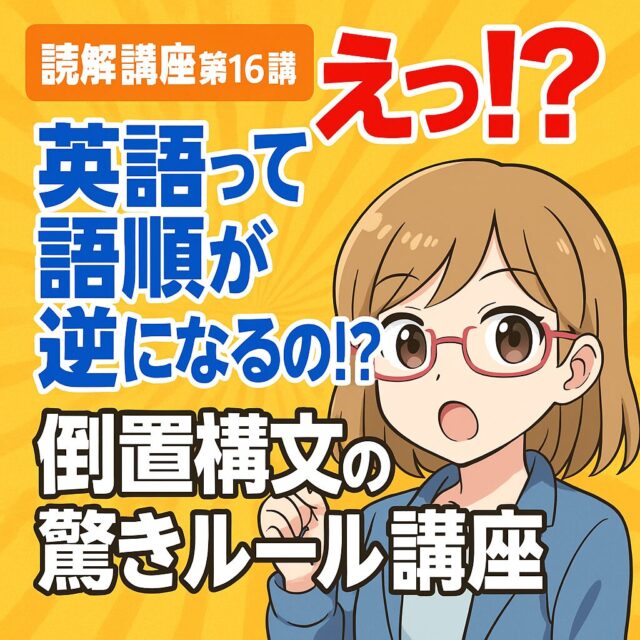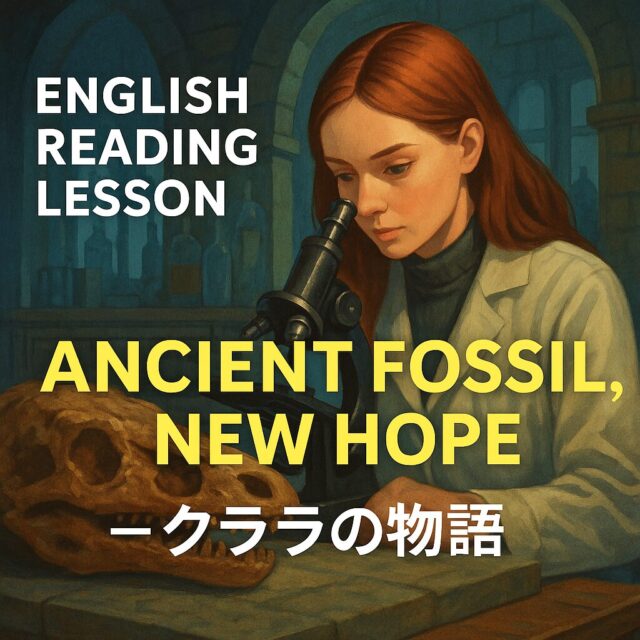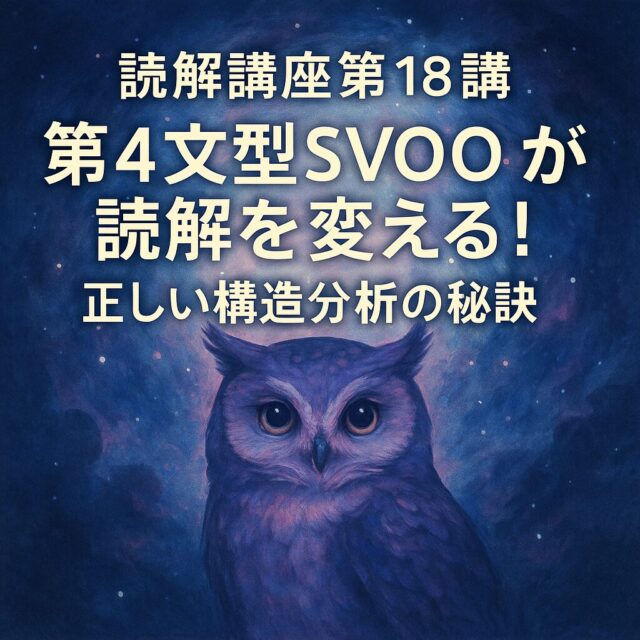📘 読解講座 第13講
「be動詞+to不定詞」で未来も命令も運命も見抜ける!?
~5つの意味を完全攻略!~
英文を読んでいると、be動詞+to不定詞という形に出会うことがあります。
たとえば、次のような文です:
He is to leave tomorrow.
「彼は明日出発する予定です」と訳されますが、実はこの be to 不定詞 には、5つ の使い方があります。文脈によって意味が大きく変わるので、読解ではしっかり見極める力が必要です。
🌟 be動詞+to不定詞の5つの意味と対応する助動詞
-
① 予定(≒
be going to)
The train is to arrive at 7 p.m.
→「列車は午後7時に到着する予定だ」
すでに決まっているスケジュールや計画に基づく未来の出来事を表します。 -
② 義務・命令(≒
should)
You are to obey the rules.
→「君はその規則に従わなければならない」
道徳的・規則的にそうすべきという意味合いを含みます。穏やかな命令・義務です。 -
③ 可能(≒
can)
No one was to be seen in the street.
→「通りには誰の姿も見られなかった」
「〜されることがなかった」「〜することができなかった」など、状況的な可能性を表します。受け身と一緒に使われることが多いです。 -
④ 意図(予定の強調)(≒
will)
We are to meet again next week.
→「私たちは来週また会うつもりだ」
予定に話し手の意志や希望が込められており、「意図的な未来」を表します。 -
⑤ 運命(≒
shall)
He was never to return home.
→「彼が再び故郷に戻ることはなかった」
「〜する運命だった」「避けられない未来」といった重みのある意味合いで、文語的に使われます。
💡 ポイント:
be to不定詞は「未来・命令・可能・意志・運命」など、幅広い意味を持つ文脈依存型の表現です。
それぞれの意味は、対応する助動詞のイメージと結びつけて理解するのがコツ!
📝 補足:助動詞との関係をもう少し深く
🔹 義務=should とする理由
「You are to obey the rules.」という文は、「You should obey the rules.」と非常に近い意味になります。
be to不定詞の義務用法は、道徳的・社会的な“すべき”というニュアンスを持つため、must よりも should に近いとされることが多いのです。
つまり、強制力のある命令というより、守るべき当然のルールというような柔らかい義務が表現されています。
🔹 運命=shall の正体
「He was never to return home.」のように、be to不定詞には避けられない運命や決定された未来を表すことがあります。
この意味合いは、shall の文語的・古風な用法と非常に似ています。
例えば、
We shall meet again.このような文は、ただの意志を超えて「定められた未来・宿命」を静かに語る表現です。
(私たちは再び会う運命なのです)
よって、be to不定詞(運命)≒ shallという対応は、学習上の整理として非常に有効です。
💡 補足まとめ:
be to不定詞の義務用法は「should」のような柔らかい義務、
運命用法は「shall」のような荘厳で避けられぬ未来、と理解すると記憶に残りやすいです。
Q1. 文脈から意味を見抜こう!(和訳問題)
He was to become one of the greatest composers in history, though he died young and lived in poverty.
▼ 解説を見る
・主語 (S):
He・動詞 (V):
was・構文:
be to 不定詞(「〜する運命にあった」)🔍 前半:to become one of the greatest composers in history
・
to: 不定詞マーカー・
become: 「〜になる」 — SVC構文を作る動詞・
one of the greatest composers: 補語(C)・
in history: 補語を修飾する前置詞句(「歴史の中で」)📌 この部分全体で「歴史上最も偉大な作曲家の一人になる運命にあった」という意味になります。
🔍 後半:though he died young and lived in poverty
・
though: 譲歩の接続詞(〜だけれども)・
he died young: died の補語に young・
lived in poverty: in poverty は lived を修飾(「どのように生きたか」)→ この後半は、背景情報(譲歩)として、主節の「栄光ある運命」と対比を生んでいます。
💡 意味判断:
「若くして亡くなった」「貧しい暮らしだった」
→ にもかかわらず、「歴史に残る存在になる運命だった」と語られていることから、
→ この
be to 不定詞 は運命の用法(≒ shall)であると判断できます。
was to 〜 のように be to不定詞が過去形で使われるとき、→ 「〜する運命だった」「〜するはずだったが叶わなかった」といったニュアンスを表します。
特に今回のように
though で困難な過去が語られ、主節で大きな成功が描かれる場合、→「そのような成功は運命づけられていた」という含みを読み取るのがコツです!
▼ 和訳を見る
彼は若くして亡くなり、貧困の中に生きたが、歴史上最も偉大な作曲家の一人となる運命にあった。
Q2. 文脈から意味を見抜こう!(和訳問題)
No help was to be found in the deserted village, and the traveler grew desperate.
▼ 解説を見る
・主語 (S):
No help・動詞 (V):
was・構文:
be to 不定詞(受動態) — was to be found🔍 was to be found
・
was: be動詞の過去形(過去の文脈)・
to be found: 「見つけられることになっていた」→ しかし文脈的に、見つけられなかった(=「助けは見つけられなかった」)と読み取れます。
🔍 in the deserted village
・「人のいない村で」 — 場所を表す前置詞句で、
found(動詞)を修飾しています。🔍 and the traveler grew desperate
・「旅人は絶望的になった」 — grow + 形容詞(SVC)構文
💡 意味判断:
この
be to 不定詞 は「〜されることがなかった」という文脈から、可能(≒ can)の否定的ニュアンスと判断できます。受動態 + be to 不定詞 が使われているときは、
→ 「〜されることができなかった」= 可能(≒ can) の意味になることが多いです!
読解では、この形に注意して「できた/できなかった」の文脈を見抜きましょう。
▼ 和訳を見る
その人けのない村では助けを見つけることはできず、旅人は絶望していった。
Q3. 文脈から意味を見抜こう!(和訳問題)
We are to begin the ceremony at noon, so please make sure everything is ready by then.
▼ 解説を見る
<主節>
・主語 (S):
We・動詞 (V):
are・構文:
be to 不定詞 — are to begin・目的語:
the ceremony・副詞句:
at noon(時間の指定)<命令文>
・
so: 接続詞(「だから」)・
please: 丁寧な依頼語句(命令の和らげ)・
make sure: 「〜を確実にする、〜するようにしておく」・
everything is ready: make sure の目的語にあたる内容文(主語+動詞+補語)┗
everything: 主語、is: 動詞、ready: 補語(状態を表す形容詞)・
by then: 前置詞句(「その時までに」)— is ready を修飾する副詞句💡 意味判断:
「正午に始める」+「それまでに準備しておくよう依頼」
→ これは単なるスケジュールではなく、「私たちがそうするつもりである」「その前提で行動してほしい」という意志的ニュアンス。
→ よって
be to 不定詞 はこの文脈で意図(≒ will)を表しています。
「be to 不定詞」が主語=話し手自身で使われるときは、
→ 意図・意思を表す場合がある(≒ will)
特に依頼・指示・注意喚起と組み合わされると、この意味になることが多いです。
▼ 和訳を見る
私たちは正午に式を始めるつもりです。それまでにすべての準備を整えておいてください。
Q4. 文脈から意味を見抜こう!(和訳問題)
All students are to submit their assignments by Friday, or they will receive no credit for the course.
▼ 解説を見る
<前半:be to 不定詞の義務用法>
・主語 (S):
All students・動詞 (V):
are・構文:
be to 不定詞 — are to submit・目的語:
their assignments・副詞句:
by Friday(期限)<後半:or they will receive no credit for the course>
・
or: 等位接続詞(「さもなければ」)・主語 (S):
they(= All students)・助動詞 (M):
will・動詞 (V):
receive・目的語:
no credit・副詞句:
for the course — 前置詞句で credit を修飾✅ 補足: ・
no credit for the course:「この講義に対して単位が一切与えられない」→ これは ペナルティの条件として提示されており、
or が導く **否定的な帰結** を構成しています。
💡 意味判断:
「金曜までに提出せよ」「提出しなければ単位は与えられない」
→ この文脈から「提出する義務がある」と読み取れる。
→ 命令・規則的な強制ではあるが、語調はあくまでshould(すべき)に近い。
よって
be to 不定詞 はここで義務の用法(≒ should)と判断できます。
be to 不定詞 は「すべきこと・従うべきルール」が文脈にあると、→ 義務(≒ should)の意味で使われます。
強制(must)ほど厳しくないけれど、「守るのが当然」とされるニュアンスです。
▼ 和訳を見る
すべての学生は、金曜までに課題を提出することになっている。提出しなければ、この講義の単位は与えられない。
Q5. 文脈から意味を見抜こう!(和訳問題)
The president is to visit the affected area tomorrow to speak with local leaders and assess the damage.
▼ 解説を見る
・主語 (S):
The president・動詞 (V):
is・構文:
be to 不定詞 — is to visit・目的語:
the affected area・副詞:
tomorrow・不定詞句:
to speak with local leaders and assess the damage┗ 目的・意図を表す副詞的用法の to不定詞(何のために訪問するのか)
💡 意味判断:
「明日、現地を訪れる」「被害を調査し、指導者と会うため」
→ これはすでに日程や行動が決まっている予定であるとわかります。
→ よって
be to 不定詞 はここでは予定(≒ be going to)の用法と判断できます。
be to 不定詞 の「予定」用法は、→ 具体的なスケジュールや計画が文脈に含まれているときによく使われます。
「誰が」「いつ」「何をする」が明確に書かれていると、この用法のサインです。
▼ 和訳を見る
大統領は明日、被災地を訪れ、地元の指導者たちと面会し、被害の状況を確認する予定です。
🔮 次回予告:読解講座第14講
「〜ing」って、いろんな顔を持ってるけど…それぞれ何が違うの!?
第14講では、「ing形」の4つの使い分けにフォーカス!
- 動名詞(I enjoy reading.)
- 進行形(She is reading a book.)
- 現在分詞(The girl reading a book is my sister.)
- 分詞構文(Reading a book, she smiled.)
似ているようで役割も位置もバラバラな4つの「ing形」。
読解の中で見分けるポイントを一つずつ丁寧に整理していきます。
🪄 「主語があるか?」「動詞の代わり?」「名詞っぽい?」「文頭にある?」
あなたの中の “ing迷宮”、次の講義で完全クリアしましょう!

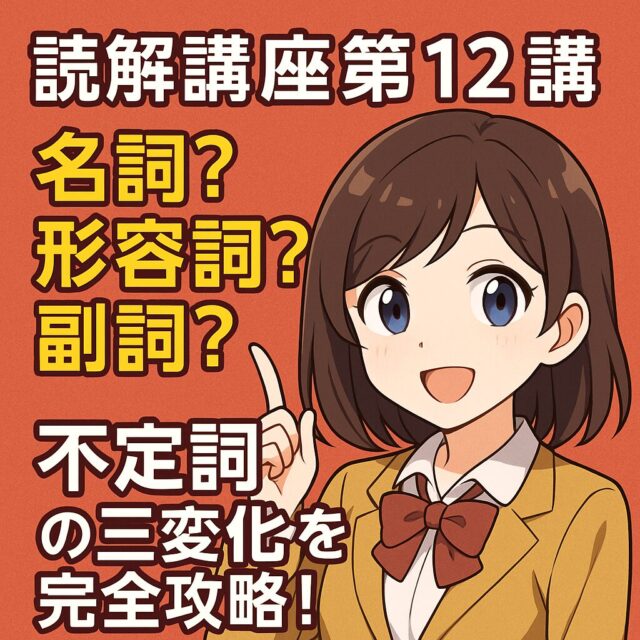

-640x640.jpg)